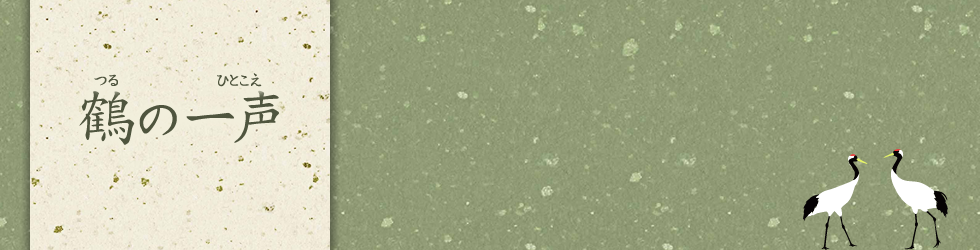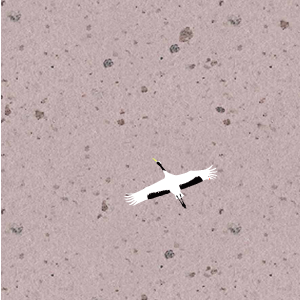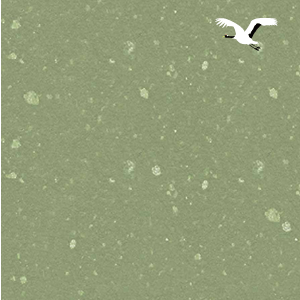杣人伝 その13
丸山は、二日前に、教頭の朝倉にその日の十時に校長室に来るように言われていた。
まだ、始業式が翌日、入学式が二日後ということで生徒は登校していない。
職員室では、教師だけが休み明けの新学期や、入学式の準備に追われたり雑談をしているくらいで、職員室を一歩出ると校内は静まり返っていた。
丸山がノックをして校長室に入ると、校長と朝倉がソファーで向かい合って話をしているところだった。
朝倉が立ち上がって、丸山に自分の隣に座るよう席を勧めた。
関矢は、朝倉と丸山が腰を下ろすのを見計らって話を切り出した。
「実は、突然ですが、丸山先生のクラスに今度男子生徒が編入することになりました」
一応、定員は四十名ですので、一人増えても三十八名ですから問題はありません。ただ、その男子生徒はちょっと特別な事情がありまして、今まで学校に通ったことがありません」
関矢の話に、丸山が不思議そうな顔をしたが、そのまま話を続けた。
「学校には行っておりませんが、中卒並みの学問は受けて」と言いながら、我ながらこの頃使わない学問と言う言葉が出たことに気付いて、「それなりの教育は受けています」と言い直した。
「確かに、彼は学習期間は短いかも知れませんが、並みはずれた能力を持っていますし、何よりも、運動神経は潜在的な優れた能力を持っています。」朝倉が繋いだ。
朝倉は、実際にツルギ少年の運動能力を見たわけではなかったが、これまでの関矢の話から相当な能力があることは伺えていたので、つい、知っているような口調になった。
「ただ、九州の山中で育てられたので方言が強く、言葉が慣れるまでは少し時間がかかるかも知れません。それに世間慣れしていません」
丸山は、すごい田舎の子なんだろうと想像しながら二人の話を聞いた。
「例えば、まだ生まれてこの方、彼はバスや電車に乗ったことがなく、乗り物と言えば、今度九州から上京する際に乗った車と飛行機が初めてだというくらいです」
矢部の奥地で、朝倉と待ち合わせて、八女工業の教師の車で福岡空港まで行き、それから空路大阪の伊丹空港、そして更に迎えの車で滋賀の神主の家まで行ったのが最初の体験だった。
車や飛行機などの乗り物があることは既に学んでいたものの、乗るのは初めてで、最初は驚いていららしいが、その後、滋賀から東京に来る時になると、既に驚く様子もなかったと関矢は朝倉から聞いていた。
それを聞いて、あまり物事に動じない丸山が、初めて驚きの表情を見せた。
今度は関矢が引き継いで、「その子は関矢司郎と言って、名前の通り、私の縁戚の者で両親が事故で亡くなったものですからね、滋賀の本家の者が引取り、高校の三年間を私が預かって、私の家から通わせることにしたんですよ」
今度は朝倉が「それで、入試には準備時間が無かったので、彼の運動能力に期待してスポーツ特待と言うことでの編入ということにしました。丸山先生は陸上部の顧問でもあるので、大変だと思いますが、何とかご理解を得ておきたいと、今日来てもらったんです」
「よろしくお願いします」関矢も朝倉に合わせて頭を下げた。
今まで黙って二人の話を聞いていた丸山が応えた。
「事情は分かりました。私にとってクラスの子供たちは、どにな事情があろうと、分け隔てなく育てるつもりですから問題ありません」
「それを聞いて安心しました」そう言って朝倉が続けた。
「実はもう一つだけ。若いだけに、生活には暫くすれば慣れてくると思いますが、先ほど言いましたように、彼は運動能力が優れているのですが、その、特別に優れていて、それが世間に知れると、彼の為にならない事情があるものですから」
朝倉の言う言葉に、丸山は不思議な気持ちだった。
それだけの特出した能力があれば、いろんな大会で活躍できて、その少年の将来のためになるはずではないか。そう思った。
しかし、日頃から尊敬している校長、教頭が口を揃えて言うのだから、何か深い事情があるのだろうと、ここでこれ以上聞いてはいけないような気がして「わかりました。そのように努めます」とだけ答えて、編入生の書類を預かったのだった。
丸山は、そう言いながらも、陸上部顧問としては、その子がどんな運動能力を持っているのか見てみたいと思った。
それに、丸山も物心つかない内に両親を亡くして、親戚に育てられた過去があり、自分の運命のようなものを感じたのだった。
三沢みずきは、編入生、とは言っても新入生と一緒に一年生の授業が始まるのだから、自分たちと何も変わらないなと思いながら、後方の机から、丸山の横に立っている、その男子生徒に目をやった。
丸山の紹介が終わって、男子生徒はうつむいていた顔を上げた。
みずきは思った「私、この人、どこかで見たことがある」「どこで会ったのだろう」
「でも、九州の田舎から初めて東京に出てきたばかりだと言うから、そんなはずないか」
自分で問答を繰り返した。
みずきは、背の高い方だったので、後列から二列目の廊下側だったが、その関矢の席は最後列の窓際に決まった。
関矢司郎と紹介された編入生が、丸山に促されてその指定された席についた。
この季節、ちょうどグランド側の窓の方から陽光が入ってくる。
みずきは、関矢の逆光を浴びた姿を見て、はっとした。
「そうだ、この顔は、あの時の!ずっと頭の中に引っかかっていた、子犬を抱いた少年」
みずきは、あの坂の上で子犬を抱いて黙って逆光の中に立っていた、あの時の情景を思い出していた。
その日は、入学式と、クラスでの配布物の説明など午前中で終わり、午後はクラブに入部する者は、部室に顔を出したり、クラスの中でも人の輪が出来て盛り上がったりしていたが、あの編入生の姿はもうなかった。
窓の方に駆け寄ってグランドの方を見ると、各クラブの先輩たちが下校する新入生に入部を勧めている。
みずきは、すでに入部を決めている吹奏楽部の部室に顔を出してから、説明会を終える母の美津子と校門で待ち合わせていた。
今日は入学のお祝いに、途中のお気に入りのレストランで姉の慶子も合流して、三人でランチを楽しむことになっていたのだった。
つづく